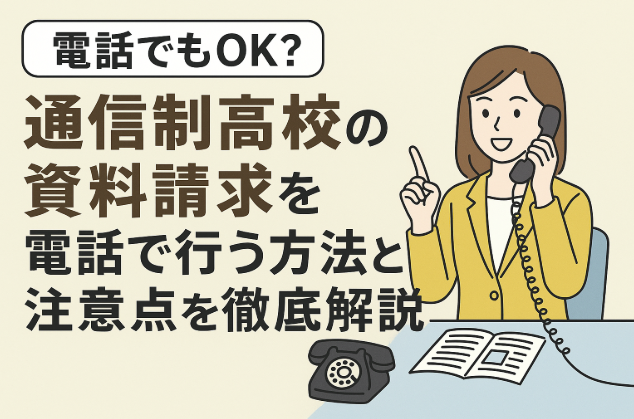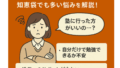|通信制高校の資料請求は電話でもできる?基本の確認ポイント
通信制高校に興味を持った際、「まずは資料を取り寄せて検討したい」と考える方は多いでしょう。一般的にはインターネットを使ったWebフォームからの資料請求が主流ですが、電話による資料請求も可能なケースが多く存在します。
■ 電話で資料請求できる理由とメリット
電話での資料請求は、以下のようなニーズを持つ方に適しています。
-
ネット操作が苦手な方や高齢の保護者の方
-
特定の学校について詳細を口頭で確認したい方
-
資料の送付時期や追加説明が必要な方
通信制高校の多くは、資料請求用の専用ダイヤルや入学相談窓口を設置しており、電話でも丁寧に対応してくれる体制を整えています。電話口では、必要事項(名前・住所・希望コースなど)を伝えるだけで資料の発送手続きが完了します。
■ 電話で資料請求できる通信制高校の例
実際に、以下のような全国規模の通信制高校では、電話対応による資料請求が可能です。
-
第一学院高等学校:0120から始まる入学相談ダイヤルあり
-
鹿島学園高等学校:全国共通フリーダイヤルで受付中
-
N高等学校・S高等学校(KADOKAWA運営):一部エリアでは電話対応も実施
-
飛鳥未来高等学校:電話での資料請求や見学予約が可能
これらの学校では、オペレーターが常駐している時間帯(平日9:00〜18:00など)に電話すれば、即日対応してもらえるケースが多いです。
■ 資料請求の際に聞かれる主な内容
電話で資料請求する際には、以下の項目を事前に確認しておくとスムーズです。
| 質問内容 | 回答例 |
|---|---|
| 名前(ふりがな) | 例:山田太郎(やまだたろう) |
| 現在の学年・学校名 | 例:中学3年、○○中学校 |
| 進学希望時期 | 例:来年4月から |
| 資料の送り先住所と郵便番号 | 例:〒802-0001 福岡県北九州市○○町… |
| 電話番号・連絡先メール | 携帯番号または自宅番号、任意でメール |
※学校によっては希望コースや相談内容を聞かれることもあります。
■ 電話で請求できないケースもある
すべての通信制高校が電話受付をしているわけではありません。特に「資料はWebからのみ受け付けます」と明記している学校も一部あります。また、個人情報保護の観点から、本人確認のためにWeb申請を推奨している場合もあります。
こうしたケースでは、**「電話で仮予約 → Webで正式申請」**という流れになることもあるため、学校の公式サイトを事前にチェックしましょう。
【参考リンク・権威ある情報元】
-
文部科学省|通信制高校の制度について
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/04062101.htm -
全国の通信制高校ガイド(文科省監修)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tsushin/ -
高校教育に関する相談窓口一覧(全国)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/04062103.htm
Webでの資料請求と電話請求の違いとは?メリット・デメリット比較
通信制高校の資料請求には「電話」と「Web」の2つの主要な方法がありますが、それぞれに明確な違いとメリット・デメリットがあります。自分や保護者の状況に応じて、適切な方法を選ぶことが重要です。
■ Webからの資料請求が主流になっている理由
現在、ほとんどの通信制高校では、Webサイトに資料請求フォームが用意されており、そこから24時間いつでも申し込むことが可能です。この仕組みが主流となっている背景には、以下のような理由があります。
-
手続きが自動化されているため、学校側も処理がスムーズ
-
記入ミスが少なく、住所・希望内容などを正確に把握できる
-
発送管理がデジタルで行えるため、到着の遅延を減らせる
-
保護者や生徒本人が自分のタイミングで申し込める
加えて、フォームによっては「オンライン説明会への申込」「キャンパス見学の予約」などもセットでできるため、よりスムーズな進学準備が可能です。
■ 電話請求のメリットとシーン別活用例
一方、電話による資料請求は、デジタルに不慣れな方や、即時に詳細な説明を聞きたい場合に向いています。
たとえば次のようなケースでは電話請求が適しているといえます。
-
保護者が高齢でパソコン操作が難しい
-
Webフォームで送信エラーが起きた
-
在宅での学習方法や通学頻度について細かく聞きたい
-
既に転校の意思が固まっており、話を一気に進めたい
特に、転入や編入を検討している場合は「○月の途中でも転入できるのか?」「単位の引き継ぎはどうなるのか?」といった個別性の高い質問が多いため、電話で直接確認した方が安心できることも多いです。
■ 電話 vs Web|それぞれのメリット・デメリット比較表
| 比較項目 | 電話による資料請求 | Webによる資料請求 |
|---|---|---|
| 手続きの簡単さ | 相手の誘導に従えば手続き完了 | スマホ・PC操作が必要 |
| 時間の自由度 | 平日9:00~18:00など制限あり | 24時間いつでも申請可能 |
| ミスの少なさ | 口頭なので伝達ミスや聞き間違いのリスク | 入力内容を目で確認できるため正確 |
| 詳細な相談のしやすさ | その場で相談や質問ができる | 基本的にチャットやメール対応になる |
| 資料到着の早さ | 電話でもWebでも変わらないことが多い | 学校によっては発送処理がより早い |
このように、どちらが優れているというよりも、ニーズや状況に応じて適した手段が異なるというのが実情です。
■ 併用も可能!最初はWeb→後から電話相談という使い方も
「まずは資料だけ欲しい」という方はWebで申し込み、「届いた資料を読んだうえで質問したい」という場合は後から電話相談するのが、もっとも効率的です。通信制高校ではこのような段階的アプローチを歓迎しており、「電話=入学意思がある人」だけではありません。
実際に、第一学院高等学校やルネサンス高等学校などでは、Web請求後の相談窓口を充実させており、丁寧な対応を受けることができます。
また、見学予約も電話でできる学校が多いため、「通える距離にキャンパスがあるかどうかを確認したい」という方にも適しています。
■ 入学後のサポート体制を確認するなら電話が有効
資料請求の時点で「この学校は信頼できるかどうか」を判断するのは難しいかもしれません。しかし、電話対応の質はその学校のサポート体制の指標にもなります。
たとえば、
-
言葉遣いが丁寧で誠実な対応をするか
-
難しい質問にも的確に答えてくれるか
-
無理に勧誘せず、生徒の事情を配慮してくれるか
といった点から、その学校の「風土」や「教育姿勢」を感じ取ることができます。これこそ、Web申請では得られない電話相談の強みといえるでしょう。
電話で資料請求する際の注意点とマナー|トラブルを避けるために
通信制高校の資料請求を電話で行う際には、いくつかの重要なマナーや注意点があります。ただ話せば終わるというわけではなく、相手は教育機関の担当者であり、生徒や保護者の対応にも気を配っている点を理解しておくことが大切です。
この記事では、トラブルを避け、スムーズに資料請求を完了させるための「電話マナー」と「具体的な注意点」を詳しく解説します。
■ 電話をかける時間帯は「平日の日中」がベスト
まず最初に気をつけたいのが、電話をかける時間帯です。通信制高校の多くは平日9:00〜17:00または18:00までの対応時間を設定しています。
【NGな時間帯の例】
-
土日祝(休校している場合が多い)
-
朝早すぎる時間(8時前)
-
夕方18時以降(担当者が不在の可能性)
また、お昼休憩の時間帯(12:00〜13:00)は電話がつながりにくいこともあるため、避けた方がよいでしょう。
【おすすめの時間帯】
-
平日10:00〜11:30
-
平日14:00〜16:30
上記の時間帯であれば、オペレーターや入学相談スタッフが対応しやすく、落ち着いたやり取りができる可能性が高いです。
■ 話す前に準備しておきたい5つのポイント
電話の途中で情報が足りなくなると、説明がうまく進まない場合があります。事前に以下の5つの情報をメモしておくと、スムーズな対応が可能です。
-
自分または子どもの名前(ふりがな含む)
-
現在の学年と学校名
-
進学希望の時期(例:来年度4月から)
-
住所・郵便番号(資料送付先)
-
希望するコースや質問したい内容(例:通学頻度、単位取得方法)
また、メモ帳や録音機能を使って「説明内容を記録」しておくのもおすすめです。後から家族と共有する際にも役立ちます。
■ 話し方のマナー|押さえておきたい基本的な言い回し
教育機関にかける電話である以上、最低限の言葉遣いやマナーを守ることは重要です。以下に基本的なやり取りの例を紹介します。
(電話をかける例)
📞
「お忙しいところ失礼いたします。〇〇市に住む山田と申します。貴校の資料を拝見したくお電話させていただきました。入学を検討している子ども(中学3年生)がいるのですが、資料を送っていただけますでしょうか?」
(聞き取れなかった場合)
「恐れ入ります。今おっしゃった内容をもう一度お願いできますでしょうか?」
(終わる際)
「ご丁寧にありがとうございました。資料の到着を楽しみにしております。失礼いたします。」
このように、礼儀正しく、はっきりとした口調で話すことが重要です。相手も慣れているので、必要以上に緊張する必要はありません。
■ 個人情報の伝え方にも注意を
電話で資料請求をする際には、個人情報(氏名・住所・電話番号など)を口頭で伝えることになります。以下の点に注意しておきましょう。
-
周囲に他人がいない場所でかける(カフェ・電車内などは避ける)
-
書類や資料に書いてある住所を見ながら正確に伝える
-
漢字の説明は「山田の“山”は“富士山の山”です」のように伝える
-
電話番号・郵便番号は、ゆっくり区切って話す
特に住所や電話番号の聞き間違いは、資料が届かない原因になりますので、聞き返されても丁寧に繰り返すことを心がけましょう。
■ 無理な勧誘があった場合はどうする?
通信制高校の中には、説明会への参加や面談を強く勧めてくる場合もあります。ただし、あくまで資料請求のみを希望する場合は、「まずは資料を確認してから検討します」と丁寧に断って構いません。
しつこい勧誘や不快な対応があった場合は、以下の公的窓口に相談することも可能です。
-
文部科学省「教育相談窓口一覧」:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/04062103.htm
-
消費者ホットライン:188(最寄りの消費生活センターへ接続)
ただし、実際には強引な勧誘を行う学校は少数です。丁寧な対応ができる学校ほど信頼性が高く、入学後のサポートも充実している傾向があります。
■ よくある電話トラブルと対処法
| トラブル例 | 解決方法 |
|---|---|
| 担当者が不在だった | 後日、再度電話をかけ直す |
| 名前の漢字を間違えられて資料が届かない | メールや再電話で訂正を依頼 |
| 口頭で伝えた内容を忘れてしまった | メモや録音機能を使っておく |
| 番号を間違えて他人の学校にかけた | 公式サイトの番号を必ず確認して電話する |
資料請求のあとはどうする?比較・見学・進路相談のステップガイド
通信制高校へ資料請求をした後、「届いたけど、どうすればいいの?」と悩む方も少なくありません。資料を取り寄せただけでは、学校の実際の雰囲気や通学の負担、学習サポート体制までは見えてこないのが現実です。
この見出しでは、資料請求後に取るべき3つのステップを詳しく解説し、最終的にミスマッチのない学校選びを実現するためのガイドラインを紹介します。
■ ステップ①:資料は届いたらすぐに開封&チェック!
まずは、届いた資料を開封して目を通すところから始めましょう。パンフレットの中には、次のような内容が含まれていることが多いです。
| 内容 | 確認ポイントの例 |
|---|---|
| 学校の概要・教育理念 | 自分の学び方に合いそうか? |
| 学費・入学金・設備費の一覧 | トータルでいくらかかる? |
| カリキュラム(週何日通学か) | 通学が必要?完全オンラインも可? |
| 卒業までの単位取得スケジュール | いつ卒業できる?中退や転校の影響は? |
| 資格取得・大学進学の実績 | 就職や進学サポートはあるか? |
| 学校行事・イベントの紹介 | 自分に合った学校生活ができそうか? |
また、細かく比較するために「チェックリスト」を作っておくと便利です。比較項目を一覧化することで、どの学校が自分のニーズにマッチしているかが一目でわかるようになります。
■ ステップ②:気になる学校を絞って資料を比較する
複数の学校に資料請求をした場合、それぞれの特徴が混ざってしまうこともあります。ここで必要なのが、ポイントを絞って比較することです。
以下は、比較に役立つ主な項目です。
| 比較項目 | 比較ポイント |
|---|---|
| 通学スタイル | 毎日通う?週1通学?自宅学習中心? |
| 授業形式 | Zoomなどでの双方向型?録画型?テキスト型? |
| 学費 | 初期費用・月謝・教材費などトータルでいくら? |
| サポート体制 | 担任制?メッセージでの質問対応あり? |
| 卒業率・進学実績 | 実際にどれくらいの生徒が卒業している? |
| 校則・ルール | 髪型・服装など自由かどうか? |
比較表を自作して、A高校・B高校・C高校と並べていくと、「学費は安いけど通学が必要」「進学実績は高いけど厳しそう」など、相対的な判断がしやすくなります。
■ ステップ③:オンライン説明会・個別相談・学校見学へ進もう
資料で気になった学校があれば、次のステップは**「人と話す」こと**です。多くの通信制高校では、以下のような相談機会が設けられています。
-
オンライン説明会(Zoom・Teamsなど)
-
個別進路相談(1対1で質問可)
-
校舎見学・体験入学(実際に訪問して教室を見られる)
オンライン説明会は自宅にいながら参加でき、学校の雰囲気や担当者の対応がよくわかる絶好のチャンスです。特に、「いきなり見学に行くのは緊張する」という方にはおすすめです。
事前に質問リストを作っておくと効果的です。例えば以下のようなことを聞くと良いでしょう。
-
転入する場合、単位の引き継ぎはどうなるか?
-
スマホやゲームの制限はあるか?
-
不登校の生徒がどれくらいいるか?
-
保護者向けのサポートはあるか?
■ 説明会や相談に参加するメリット
参加することで、単にパンフレットを読むだけではわからなかった学校の内面に触れることができます。
| 参加方法 | メリット |
|---|---|
| オンライン説明会 | 自宅でラクに参加できる/録画視聴できる学校も |
| 個別進路相談 | 自分の状況に合ったアドバイスがもらえる |
| 学校見学・体験入学 | 実際の生徒の様子がわかる/校舎の雰囲気が見える |
特に、進路に悩んでいる人や不登校経験者にとっては、先生との相性や雰囲気が重要です。ぜひ積極的に参加しましょう。
■ 情報整理と家族での話し合いも忘れずに
説明会や個別相談を経て、情報がそろったら、家族と一緒に最終判断をしましょう。家族が応援してくれる環境を整えておくことも、通信制高校での成功につながります。
【話し合うポイント】
-
通学頻度や学習スタイルに無理はないか
-
金銭的に続けられるか
-
精神的・身体的な負担は少ないか
-
卒業後の進路のイメージはできるか
志望校を決めるときのポイント|後悔しないための最終チェックリスト
資料請求・比較・相談と進めてきた中で、いよいよ「どの通信制高校にするか」を決めるタイミングがやってきます。この段階で迷うのは当然です。パンフレットや説明会ではどの学校も魅力的に見えるため、最終的な決定基準が曖昧だと後悔につながることもあります。
ここでは、後悔しないための「志望校決定ポイント」と、最終確認に使えるチェックリストを紹介します。
■ 「気になる」だけでは選ばない!判断軸を明確にする
まず重要なのは、「なんとなく印象が良かった」だけで決めないことです。通信制高校は、在学中の自由度が高い分、自分に合ったスタイルかどうかを見極める目が必要になります。
決定の判断軸として、以下のような観点で整理してみましょう。
| 観点 | 判断するための問い |
|---|---|
| 学習スタイルの自由度 | 週何日通学?オンライン学習は使いやすそうか? |
| 先生・学校の雰囲気 | 相談しやすい雰囲気だったか?LINEや電話相談は? |
| 学費と支払方法 | 無理なく支払いを続けられそうか?奨学金制度は? |
| 進路支援の充実度 | 大学・専門学校・就職など希望進路に対応している? |
| 生徒層・雰囲気 | 自分と似たタイプの生徒が多そう?浮きそう? |
| 通学のしやすさ | 自宅からのアクセスは?通えそう? |
■ 特に重要なポイントは「続けられるかどうか」
通信制高校の中退率は、全日制高校より高めであるというデータもあります(文部科学省調査より)。理由はさまざまですが、「自分に合っていなかった」「モチベーションが保てなかった」「サポートが少なかった」などが代表的です。
そのため、選ぶ際の最重要ポイントは以下の2点です。
-
3年間(または2年間)無理なく通い続けられる環境か?
-
学びに対する不安や不満を相談できる体制があるか?
通学頻度や学習内容に魅力があっても、**一人で悩みを抱えることになると続かなくなります。**その意味でも、「先生との相性」「相談のしやすさ」は実は非常に大切な基準です。
■ 志望校決定のための最終チェックリスト
以下の項目にすべて「はい」と答えられる学校であれば、あなたにとって高い確率でマッチしている可能性があります。家族とも一緒にこのチェックを行ってみてください。
| 質問 | はい/いいえ |
|---|---|
| 学校の教育方針・学習スタイルに共感できる | |
| カリキュラムや通学頻度が自分の生活に合っている | |
| 学費が無理なく支払える範囲である | |
| 不登校経験や中途入学にも理解がありそう | |
| 先生や担当者の対応が親切で丁寧だった | |
| 卒業までの流れや単位取得が明確に説明されていた | |
| オンライン学習の仕組みが分かりやすく利用しやすい | |
| 進学・就職の実績があり、進路相談にも乗ってくれそう | |
| 校則やルールが自分の価値観に合っている | |
| 家族や本人が「ここなら安心」と感じている |
「いいえ」が3つ以上ある場合は、再検討するか他校も候補に入れて比較すると良いでしょう。
■ 進学前の最終ステップ|必要書類と出願準備
志望校が決まったら、出願に必要な書類や手続きを確認しましょう。多くの通信制高校では、以下の書類が必要です。
-
入学願書(学校指定の書式)
-
写真(縦4×横3cmなど)
-
在籍校の調査書または成績証明書
-
健康診断書(学校による)
-
本人確認書類(保険証・住民票など)
また、入学試験や面談の有無、締切日にも注意が必要です。
入学時期は主に4月・10月の年2回が一般的ですが、転入や編入は毎月可能な学校もあります。各校の公式サイトや電話で確認しておくと安心です。
■ もし迷ったら…公的相談機関や専門窓口も活用を
「どれが自分に合っているか最後まで決めきれない…」そんな場合は、学校以外の第三者に相談するのも有効です。
以下のような機関では、通信制高校に関する相談も受け付けています。
-
文部科学省「教育相談窓口」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/04062103.htm -
地域の教育支援センター(適応指導教室など)
-
NPO法人や進路相談団体(例:不登校支援NPO)
客観的なアドバイスをもらうことで、自分では気づかなかった選択肢が見えてくることもあります。
【まとめ】自分に合う学校選びが何よりの「成功への近道」
通信制高校の選択は、今後の進学・就職だけでなく、本人の生活リズムやメンタル面にも大きく影響します。見た目やネームバリューではなく、「自分が安心して続けられる場所かどうか」を基準に選ぶことで、きっと満足できる高校生活を送ることができるでしょう。
通信制高校だからこそ可能な夢や目標をもって学習できる環境を探してみてください。
📘通信制高校を一括で比較できる
→ ズバット通信制高校比較で資料請求(無料)