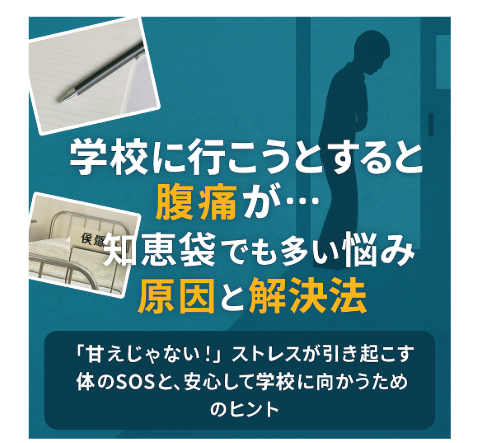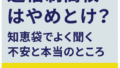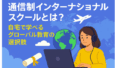学校に行こうとすると、急にお腹が痛くなったり頭が痛くなったりする——。そんな悩みは決して珍しくありません。知恵袋にもたくさんの相談が寄せられています。この記事では「学校に行こうとすると腹痛 知恵袋」というキーワードで調べる人のために、原因と対策をまとめました。厚生労働省や専門機関の情報も引用し、信頼できる知識をお届けします。

学校に行こうとすると腹痛が起こるのはなぜ?知恵袋の声と医学的な背景
「学校に行こうとすると毎回お腹が痛くなるんです…」「玄関まで行くと急にお腹が痛くなり、結局行けない」
こうした悩みは、知恵袋をはじめ多くの相談サイトでよく見かけます。質問者の多くは「自分だけおかしいのかな?」「ただの甘えなのでは…?」と不安を抱えているようですが、結論から言うと、それは決して甘えではありません。
医学的にも、強いストレスや不安が原因で腹痛が起こる現象はよく知られており、子どもにも大人にも見られる自然な反応なのです。
この記事では、知恵袋の相談事例も交えながら、「学校に行こうとすると腹痛が起きる理由」について、医学的背景とともに解説します。
知恵袋でよくある相談内容
知恵袋に投稿される悩みの多くは、次のようなものです。
-
朝になるとお腹が痛くなり、トイレから出られない。
-
学校の近くまで行くとお腹が痛くなり、途中で引き返してしまう。
-
テストの日や体育のある日など、特定の日に腹痛がひどい。
-
行こうとする意思はあるのに、体が言うことをきかない。
こうした悩みを抱えている人の中には、毎日学校を休んでしまう人もいれば、週に数回は頑張って登校する人もいます。共通しているのは、「学校に行きたい気持ちはあるのに、どうしても体がついてこない」という葛藤です。
知恵袋ではこれに対して、「甘えずに行くべき」という厳しい意見もあれば、「体がSOSを出している証拠だから休んでいい」という共感的な声もあります。しかし、正しくは、どちらでもなく、「休むべき時は休み、必要なサポートを受けるべき」というのが専門家の見解です。
腹痛の医学的背景
学校に行こうとする時に現れる腹痛は、多くの場合、ストレスが原因です。特に思春期の子どもは、大人よりもストレスに敏感で、体に現れやすいとされています。
具体的には、以下のような仕組みで腹痛が引き起こされます。
ストレスと腸の関係
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、脳と神経でつながっています。強い緊張や不安を感じると、自律神経が乱れ、腸の動きが過剰になったり、逆に鈍くなったりします。このため、お腹が痛くなったり、下痢や便秘が起きたりします。
過敏性腸症候群(IBS)
こうしたストレスによる腸の不調が慢性的に続く場合、医学的には「過敏性腸症候群(IBS)」と呼ばれることがあります。過敏性腸症候群は、腹痛や下痢、便秘が繰り返し起こるにも関わらず、検査をしても腸自体に異常が見つからない病気です。
日本小児心身医学会によると、過敏性腸症候群は小学生〜高校生にも多く見られ、特に学校に行く前の時間帯に症状が強く出るケースが多いとされています。
起立性調節障害やその他の心身症
また、腹痛だけでなく、めまいや頭痛、だるさなどを伴う場合は「起立性調節障害」の可能性もあります。これもストレスや自律神経の乱れが関与しており、学校に行こうとすると体調が悪くなる子どもにしばしば見られる症状です。
なぜ学校の時だけ起こるのか?
「学校に行く時だけ腹痛が出る」というのは、単に「嫌だからサボっている」のではなく、脳が「危険な場所に行こうとしている」と誤って認識しているからです。
実際に危険ではなくても、教室での人間関係や授業、体育の時間、発表の場面などに対する不安が強いと、脳はそれを「避けるべきもの」と判断し、体を守るために不調を引き起こします。
これは「ストレス反応」と呼ばれ、太古の昔から人間が身を守るために備わっている生理的な反応です。
無理に行くべきではない
知恵袋では「行かないと社会性が育たない」「サボりは許されない」という厳しい意見も少なくありませんが、無理に行こうとして体調を崩し、結果的に登校できる日が減ってしまうケースもあります。
厚生労働省の「子どものメンタルヘルスに関する資料」でも、「子どもが学校に行けないのは甘えではなく、心理的なストレスによるもの。無理に行かせず、まずは本人の気持ちを聞き、安心感を与えることが重要」と記されています【参考:厚生労働省 子どものメンタルヘルス】。
まとめ:体の声に耳を傾ける
学校に行こうとするたびに腹痛が起こるのは、あなたの体が「今はまだ無理」と教えてくれているサインです。知恵袋で同じような悩みを抱えている人もたくさんいます。まずは自分を責めず、医師やカウンセラー、家族と相談しながら、無理のない方法を探していくことが大切です。
学校に行けるようになるまでの道のりは人それぞれです。保健室登校や短時間登校から始める人もいれば、しばらく休んで別の学び方を見つける人もいます。どの道を選んでも、「体の声に耳を傾けること」が第一歩です。
知恵袋でもよく聞く「甘えなのか病気なのか?」の答え
学校に行こうとするとお腹が痛くなる、頭が痛くなる、めまいがする……。こうした症状について、知恵袋などの相談掲示板では「それは甘えではないの?」という厳しい意見も見かけます。実際、本人も「自分は甘えているだけなのかな」「こんなことで休んでいいのだろうか」と悩むケースがとても多いです。
しかし、結論から言うと、医学的には甘えではなく、体が発する危険信号であり、サポートが必要な状態です。この章では、知恵袋の声とともに、なぜ「甘え」ではなく「病気」や「心身のSOS」と捉えるべきなのかを説明します。
知恵袋に寄せられる厳しい意見と励ましの声
知恵袋などの質問サイトを見ると、こんな書き込みが目立ちます。
「ただの甘えです。無理してでも行くべきです。」
「社会はそんなに甘くない。学校も仕事も我慢して行くもの。」
こうした意見は、厳しく聞こえますが、決して少数派ではありません。特に親世代や、同じように苦しい思いを我慢してきた人たちは、「自分だって頑張ったのだから」と思い、厳しい言葉をかけてしまいがちです。
一方で、共感的な声も多くあります。
「私も同じでした。行こうとしても体が動かないのは甘えじゃない。」
「無理に行って体を壊したら元も子もない。休んでいいんだよ。」
つまり、意見は大きく分かれます。しかし医学的には、この症状は決して甘えではなく、体がストレスや不安で限界を感じているサインだと考えられています。
なぜ甘えではないのか?
① ストレスで体が反応している
強いストレスや不安を感じると、脳は「危険が迫っている」と判断し、自律神経を通じて体に「休め」という指令を出します。その結果、腹痛や頭痛、吐き気などの症状が現れるのです。
これを「心身症」と呼び、厚生労働省の資料にも「強い心理的な負担が体の症状として現れるのは珍しくない」と記されています【参考:厚生労働省 心身症とは】。
② 病名がつくケースもある
知恵袋の相談でも「過敏性腸症候群(IBS)と診断されました」という声や、「起立性調節障害でした」というケースが少なくありません。
これらは医学的に認められている病気で、治療やサポートが必要です。特に過敏性腸症候群は、検査をしても腸に異常がないのに腹痛や下痢が続く病気で、ストレスとの関わりが深いとされています。
③ 意志だけでどうにかなるものではない
「気合いで行ける」という意見もありますが、脳が「危険」と判断している状態では、無理に頑張ろうとするほど症状が悪化することもあります。むしろ一度休息を取り、心身を整えてからでないと、元の生活に戻るのが難しくなることもあります。
知恵袋の体験談から学べること
知恵袋には、同じように悩んだ経験をもつ人たちの声がたくさんあります。
「最初は『甘えだ』と言われて苦しかったけど、病院に行ったらIBSと言われて薬でかなり楽になった。」
「無理して登校していたら体調を崩して入院することになった。もっと早く休めばよかった。」
これらの体験談から分かるのは、「早めに対処することで回復が早くなる」ということです。自分を責めたり、「甘えかもしれない」と無理をするより、まずは医師やカウンセラーに相談するのが大切です。
親や周囲の理解も大切
周囲が「甘えだ」と決めつけてしまうと、本人はますます追い詰められ、症状が悪化してしまいます。厚生労働省の「子どものメンタルヘルス支援」では、以下のように述べられています。
「子どもが登校できないのは、怠けているのではなく、心理的・身体的な理由がある場合が多い。周囲が理解し、安心できる環境を整えることが必要。」
周囲に理解してもらうために、医師の診断書やカウンセラーの意見を活用するのも有効です。親や先生と一緒に、少しずつ無理のない方法を見つけるとよいでしょう。
甘えではなく「支援が必要な状態」
知恵袋でよく聞く「甘えか病気か」という問いに対して、答えはこうです。
「甘えではなく、支援が必要な状態です。」
心身症、過敏性腸症候群、起立性調節障害などの診断がつかなくても、ストレスが強く体に不調が出ていること自体が、すでにサインです。休息し、専門家の支援を受けるのは恥ずかしいことではありません。
まとめ:自分を責めずに、サポートを求めよう
学校に行こうとすると腹痛が起こる。これは「甘え」ではなく、「体の悲鳴」です。知恵袋の中にも、同じように悩んでいる人がたくさんいますし、その多くが「もっと早く相談すればよかった」と言っています。
無理に我慢して悪化させるよりも、まずは病院やカウンセラーに相談し、親や先生にも状況を説明して、無理のないペースで登校できる道を探していきましょう。
厚生労働省のサイトでも、不安や悩みの相談窓口が紹介されています。【参考:厚生労働省 相談窓口一覧】
自分を責めず、少しずつでいいので一歩ずつ進んでくださいね。
病院で相談するべき?どこに行けばいいの?
学校に行こうとするとお腹が痛くなる、頭が痛くなる、体がだるくなる……。こうした症状が続くと「病院に行ったほうがいいのかな?」と悩む人は少なくありません。知恵袋でも、「病院に行ったらいいのか分からない」「どこに行けばいいのか教えてほしい」という相談が多く見られます。
結論から言うと、こうした症状が続いて日常生活に支障が出ているなら、一度は病院を受診することをおすすめします。この章では、どんなタイミングで病院に行くべきか、何科を受診すればいいのか、そして受診する際に知っておきたいポイントを詳しく解説します。
知恵袋でよくある「受診すべき?」という悩み
知恵袋の相談を見ていると、以下のような声がたくさんあります。
「腹痛や頭痛が続くけど、病院で何と言えばいいか分からない。」
「本当に病気か分からないのに行ってもいいの?」
「どこの科に行ったらいいの?小児科?内科?精神科?」
こうした悩みの背景には、「病院に行ったら怒られるかも」「気のせいだったら恥ずかしい」という気持ちがあります。しかし、体の不調があるなら、気のせいかどうかに関わらず相談していいのです。むしろ、気のせいではなく体が出しているサインであることが多いので、専門家に確認してもらうことが大切です。
どんなタイミングで病院に行くべき?
以下のような場合は、一度病院に相談することをおすすめします。
-
お腹の痛みや頭痛が毎日、または週に数回以上続く。
-
痛みで授業や学校生活に支障が出ている。
-
トイレにこもってしまい、遅刻や欠席が増えている。
-
朝が特につらく、午後になると少し楽になる。
-
食欲がなく、体重が減ったり、眠れなくなったりしている。
厚生労働省の「子どものメンタルヘルス」でも、こうした症状が続く場合は専門家に相談することを勧めています【参考:厚生労働省 子どものメンタルヘルス】。
何科を受診すればいいの?
知恵袋でも特に多いのが、「どの科に行けばいいのか分からない」という声です。以下を参考にしてください。
小児科・内科
最初におすすめなのは、小児科(中学生までならOKのところが多い)や一般内科です。お腹の痛みや頭痛、吐き気などの症状について詳しく聞いてくれ、必要な検査をしてくれます。過敏性腸症候群(IBS)や起立性調節障害が疑われる場合もあります。
消化器内科
腹痛や便通異常(下痢や便秘)が特に強い場合は、消化器内科が適しています。胃腸の検査や、薬の処方、食事指導などもしてくれます。
小児心療内科・児童精神科
もし小児科や内科で「ストレスや不安が強いかもしれませんね」と言われた場合は、小児心療内科や児童精神科に紹介してもらうとよいでしょう。ここでは、心理的な不安やストレスが体に及ぼす影響について詳しく相談でき、必要ならカウンセリングや薬の提案もあります。
婦人科
生理痛が特につらい場合は婦人科も大切です。低用量ピルなどで症状を軽減できることも多いです。
受診する時に伝えるポイント
病院に行った時、「何をどう話せばいいのか分からない」という不安も多いですよね。以下のポイントを押さえておくと、診察がスムーズです。
✅ いつから症状が始まったか
✅ どのくらいの頻度で症状が出るか
✅ 症状が出るのはどんな時か(学校に行こうとした時、特定の授業の前など)
✅ 症状が強くなる時間帯(朝・昼・夜)
✅ これまでに試した対策や薬があれば、それも伝える
例えば、「2ヶ月くらい前から、学校に行こうとするとお腹が痛くなります。朝が特につらくて、休むと夕方には楽になります。」というように、具体的に話すと医師も状況を理解しやすいです。
受診するメリット
病院に行くと、次のようなメリットがあります。
-
病気かどうかが分かり、安心できる。
-
薬や生活のアドバイスをもらえる。
-
医師の診断書があれば、学校や親に説明しやすい。
-
必要なら、専門の先生を紹介してもらえる。
何よりも、「自分だけが悪いのではない」と思えることが、心の負担を軽くしてくれます。
知恵袋の体験談から
知恵袋には、病院を受診してよかったという体験談も多く寄せられています。
「病院で過敏性腸症候群と診断され、薬で楽になった。」
「小児科から児童精神科を紹介され、カウンセリングを受けて登校できるようになった。」
「生理痛は婦人科でピルを処方してもらい、学校に行けるようになった。」
このように、受診することで「ただの甘えではなかった」と分かり、気持ちが楽になる人が多いのです。
まとめ:一人で悩まず専門家に相談を
学校に行こうとすると体調が悪くなるのは、体が発するSOSです。一人で悩まず、まずは病院に相談してみてください。「こんなことで病院に行ってもいいのかな?」と遠慮する必要はありません。
最初は小児科や内科で構いませんし、必要なら他の科も紹介してもらえます。診断やサポートがあると、家族や学校にも説明しやすくなり、安心して対策ができます。
厚生労働省のサイトにも、子どもや保護者向けの相談窓口が載っていますので、ぜひ活用してください。【参考:厚生労働省 相談窓口一覧】
学校でできる工夫|保健室登校・別室登校も選択肢
学校に行こうとするとお腹が痛くなる、頭が痛くなる、めまいがする——。こうした症状が続くと、「教室に戻るのは無理かもしれない」と感じることもあります。
そんなときに知っておいてほしいのが、教室だけが居場所ではないということです。知恵袋の相談でも、「保健室登校や別室登校で少しずつ慣れていけた」という体験談が多く寄せられています。
この章では、学校で利用できるさまざまな選択肢と、その活用法を具体的に紹介します。
知恵袋で見つかる「教室がつらい」という声
知恵袋を覗いてみると、次のような悩みが目立ちます。
「学校に行っても教室に入るのが怖くて、結局帰ってきてしまう」
「保健室はいいけど、親や先生が『教室に戻りなさい』と言うのでつらい」
「体育やグループ活動で人の目が気になりすぎて苦しい」
こうした悩みはとても自然なものです。無理に教室に戻るよりも、自分が安心できる場所から少しずつ学校に慣れていく方が、結果的に長く学校生活を続けやすくなります。
教室にこだわらない「登校の形」
学校に行く=教室に座って授業を受ける、と思われがちですが、実際にはいろいろな方法があります。厚生労働省の資料でも、本人が安心して過ごせる環境を整えることが大切とされています【参考:厚生労働省 子どものメンタルヘルス】。
① 保健室登校
保健室は、多くの学校で「一時的に心や体を休める場所」として利用できます。教室が怖いときでも、保健室にいれば先生や保健の先生が見守ってくれるので、安心感があります。午前中は保健室で過ごし、午後から教室に戻る、という過ごし方も可能です。
② 別室登校
学校によっては、相談室や空き教室などを利用して、少人数または一人で過ごせる「別室登校」ができます。ここで勉強したり、自習したりすることで、他人の目を気にせず落ち着いて過ごせます。テストも別室で受けさせてもらえる場合があります。
③ 適応指導教室(教育支援センター)
各自治体には、不登校の子ども向けに「適応指導教室」や「教育支援センター」が設けられていることがあります。学校とは別の場所ですが、在籍校に出席扱いで通える場合が多いです。少人数で支援してくれるので、安心して過ごしやすいです。
④ 放課後登校・行事のみ参加
「授業は無理だけど、放課後の部活動なら大丈夫」「運動会だけは参加できる」という子もいます。無理にすべての時間に登校するのではなく、できる時間帯・イベントから参加する方法もあります。
学校に相談する方法
知恵袋の投稿を見ると、「学校の先生に言いにくい」という声もあります。しかし、学校側も状況を知ればできる限り配慮してくれるケースがほとんどです。
相談のコツは、以下のポイントを意識することです。
✅ 何がつらいのかを具体的に伝える(例:教室に入ると動悸がして苦しい)
✅ どこなら落ち着けそうか(保健室・別室・放課後など)
✅ 無理なくできる範囲から始めたいという希望を伝える
できれば、保護者と一緒に先生やスクールカウンセラーに相談するとスムーズです。
知恵袋の体験談:こんな方法で安心できた
実際に保健室登校や別室登校を経験した人たちの声も参考になります。
「最初は保健室で寝てるだけだったけど、だんだん教室に行けるようになった」
「別室でプリント学習をさせてもらい、出席扱いになった」
「適応指導教室に行ったら、同じ悩みの子がいて安心できた」
こうした体験談から分かるのは、「無理をせず、自分のペースで少しずつ」というスタンスが大切だということです。
先生や周囲に伝えにくいときは
「先生にどう言えばいいか分からない」「親に迷惑をかけたくない」という場合もあります。そんなときは、カウンセラーや保健の先生に相談するのも良いでしょう。第三者が間に入ることで、伝えやすくなることがあります。
また、厚生労働省のサイトには、無料で相談できる窓口も載っていますので、こちらも活用できます。【参考:厚生労働省 相談窓口一覧】
まとめ:教室だけが居場所じゃない
「教室に行けないから学校に行けない」というわけではありません。保健室、別室、適応指導教室、放課後……学校にはいろいろな居場所があります。知恵袋の体験談からも分かるように、まずは自分が安心できる場所で過ごし、少しずつ慣れていけばいいのです。
無理をせず、自分に合った方法を先生や家族と一緒に考えていきましょう。そして「教室に戻れなければダメ」という考えにとらわれず、一歩ずつ進んでくださいね。
家族や先生にどう伝える?プレッシャーを減らすために
学校に行こうとするとお腹が痛くなり、頭が痛くなる。そんな自分に対して、「親や先生にどう説明したらいいのか分からない」と悩む人は多いでしょう。知恵袋でも、「親が『怠けるな』『次の学校では休むな』と強く言うのでつらい」という声がたくさん寄せられています。
実際、周りからのプレッシャーは、症状を悪化させる原因にもなり得ます。
この章では、親や先生にどのように伝えればいいのか、プレッシャーを減らすための工夫や、理解を得るためのポイントについてお伝えします。
知恵袋で見つかる親や先生とのトラブル
知恵袋には、以下のような書き込みが目立ちます。
「親に『休みすぎだ、甘えるな』と言われて苦しい。」
「先生に『来年は絶対に休まないで来い』と何度も言われて泣いてしまった。」
「親も先生も私の気持ちを分かってくれない。」
こうした声からわかるのは、多くの子どもたちが、「理解してもらえない」という孤独感や無力感に苦しんでいることです。
しかし、親や先生が厳しいのは、必ずしも悪意があるわけではありません。多くの場合は「将来のために頑張ってほしい」「何とかしてほしい」という焦りや不安から強く言ってしまうのです。
なぜプレッシャーは逆効果なのか?
強いプレッシャーを感じると、ストレスホルモンが分泌され、自律神経のバランスが崩れ、さらに体調不良を引き起こします。
特に、すでにストレスでお腹や頭が痛くなっている状態の子どもにとって、叱責やプレッシャーは回復を遅らせる原因になります。
厚生労働省も、子どもの不登校や心身の不調について、「無理に叱ったり追い詰めたりすることは逆効果であり、まずは安心感を持たせることが重要」としています【参考:厚生労働省 子どものメンタルヘルス】。
どう伝えるのが良いのか?
親や先生に話すのは勇気がいることですが、以下のポイントを意識すると、理解してもらいやすくなります。
① 自分の状態を具体的に伝える
「学校に行こうとするとお腹が痛くなる」「頭がズキズキして立てなくなる」など、どんな症状がどのタイミングで起きるのか、具体的に伝えましょう。
「気分が悪い」だけだと誤解されやすいので、できるだけ詳しく話すのがポイントです。
② 気持ちも正直に話す
「本当は学校に行きたいけど、体がついてこない」
「どうしても怖くて、行くのが苦しい」
こうした気持ちも、勇気を出して伝えましょう。「怠けたいわけじゃない」ということが伝わるだけで、親や先生の見方も変わることが多いです。
③ 医師やカウンセラーの意見を活用する
もし病院やカウンセラーに相談しているなら、診断書やアドバイスを親や先生に見せるのも有効です。
第三者からの言葉があると、理解してもらいやすくなります。
知恵袋の体験談:こうして理解を得た
知恵袋には、親や先生に理解してもらえた体験談もあります。
「診断書を見せたら親も納得してくれて、協力してくれるようになった。」
「カウンセラーの人と一緒に先生に話したら、別室登校を提案してくれた。」
「母に泣きながら気持ちを話したら、初めて抱きしめてくれた。」
最初は厳しかった親や先生も、本人の本当の気持ちを知ったり、専門家の意見を聞いたりすると、協力的になるケースがほとんどです。
プレッシャーを減らすための工夫
理解してもらった後も、無理のない範囲で学校生活を続けるために、次のような工夫もしてみましょう。
✅ 無理に毎日登校しようとしない。まずは週1回、1時間だけでもOK。
✅ 保健室や別室、適応指導教室など、自分が落ち着ける場所を活用する。
✅ 家族と一緒に学校と相談し、できる範囲の登校計画を立てる。
✅ カウンセラーや信頼できる先生と定期的に話す時間を作る。
「全部完璧にやらなきゃいけない」という思い込みを手放し、少しずつ進むことが大切です。
まとめ:一人で抱え込まないで
親や先生に話すのはとても勇気がいることですし、最初は理解されないこともあるかもしれません。けれども、あなたの体や心のつらさは、きちんと伝えれば必ず届きます。
知恵袋の体験談でも、多くの人が「もっと早く話せばよかった」と感じています。
無理をして症状を悪化させる前に、ぜひ一歩踏み出してみてください。
もし直接伝えるのが難しいときは、手紙やメモに書いて渡したり、カウンセラーや医師に間に入ってもらったりする方法もあります。厚生労働省の相談窓口も、困ったときは頼りになります。【参考:厚生労働省 相談窓口一覧】
通信制高校だからこそ可能な夢や目標をもって学習できる環境を探してみてください。
📘通信制高校を一括で比較できる
→ ズバット通信制高校比較で資料請求(無料)